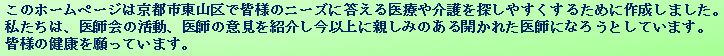まとめ)2025年度 第1回コメディカル在宅医療推進協議会
東山医師会2025年度第1回コメディカル在宅医療推進協議会報告
2025年7月26日ウエスティン都ホテル京都にて52回目となる会を催しました。
出席者はコメディカル42名、東山医師会6名、事務所50名でした。京都府医師会理事、西山病院院長、西村 幸秀先生にご講演頂きました。テーマは「認知症対策について〜BPSDガイドライン(第3版)も含めて」でした。
京都における認知症医療は、認知症サポート医を中心にかかりつけ医、地域包括支援センター、ケアマネージャー、介護事業者などが連携し、支援が行われています。
認知症予防の考え方は三段階に分かれます。一次予防では地域包括支援センターや、地域での社会参加活動を通して、社会的孤立の解消、役割を持つことにより認知症の発症を遅らせ、発症リスクを低減します。二次予防では家族、かかりつけ医などから相談があった時に速やかに認知症疾患医療センター、初期集中支援チーム、地域包括支援センターによる介入を行い早期発見早期対応につなげます。三次予防では適切な治療やリハビリテーションの継続により、認知症の進行、遅延に努めます。三次予防では生活機能の維持に努め、周囲のものが患者自身の視点に立った、ケアとストレスの除去をすることで、BPSDの予防と緩和につながります。
BPSDへの対応の原則です。緊急性が高く、速やかな薬物治療の開始を要するような精神症状が認められた場合には、認知症疾患医療センターを含めた認知症専門医がいる医療機関を紹介します。かかりつけ医、認知症サポート医で対応する場合には以下のことを考慮し必要時に認知症疾患センターを含めた認知症専門医と連携します。
・せん妄の除外
・BPSD様症状を引き起こしうる病態の除外
・BPSD様症状を引き起こしうる薬剤の除外
・レビー小体型認知症の可能性
BPSD治療のアルゴリズムです。まず、誘因や環境要因を探り、家族や介護者とその改善を図る非薬物的介入を優先します。確すべきことは前項のような、除外すべき原因がないと判断されれば、更に次の項目を確認しそれぞれ内服を選択します。
・幻覚、妄想
・易刺激性、焦燥性興奮
・不安、抑うつ
・アパシー
・睡眠障害
BPSDに対する薬剤開始後は服薬状況とともに副作用の出現に留意します。
薬剤についてです。
抗認知症薬では、症状の進行抑制について、アルツハイマー型認知症はコリンエステラーゼ阻害薬(ドネペジル、ガランタミン、リバスチグミン)および、メマンチン、レビー小体端 認知症はドネペジルが保険適用を受けています。BPSDでは憎悪することがあり注意が必要です。
抗精神病薬はBPSDに使用する場合には薬剤のリスク、ベネフィットを共有し、本人の意向も考慮し使用の可否を決定します。有効性を評価し、長期使用は避けるようにします。
睡眠に関しては、まずは睡眠環境を整えたうえで、患者のリスク、ベネフィットを考慮して使用の可否を決定します。
最後に高齢者の運転に関する問題です。しばらく前から高齢ドライバーの運転免許の自主返納の話題が出るようになっています。このような場合は相談窓口#8080、または京都府警察本部運転免許試験課臨時適性検査係、京都駅前運転免許更新センター、府内警察署交通課が相談を受け付けているそうです。
以上のようなご講演の内容でした。
その後、テーブルごとに今回のテーマに沿い、各々が現在関わっている認知症の患者さんの問題点につき話し合いました。参加者それぞれに患者さんの認知症、およびBPSDに対しどのように接するべきか悩んでいることが分かり、皆さんの悩みを共有できました。
超高齢化社会であれば必ず直面する認知症の問題に関し、皆関心はあるのですが、疑問も多いため、今回のご講演は大変ありがたいものでした。西村先生、大変ありがとうございました。又、参加者の皆さまもご参加いただきありがとうございました。次回の会もご参加お願いいたします。
→案内へ